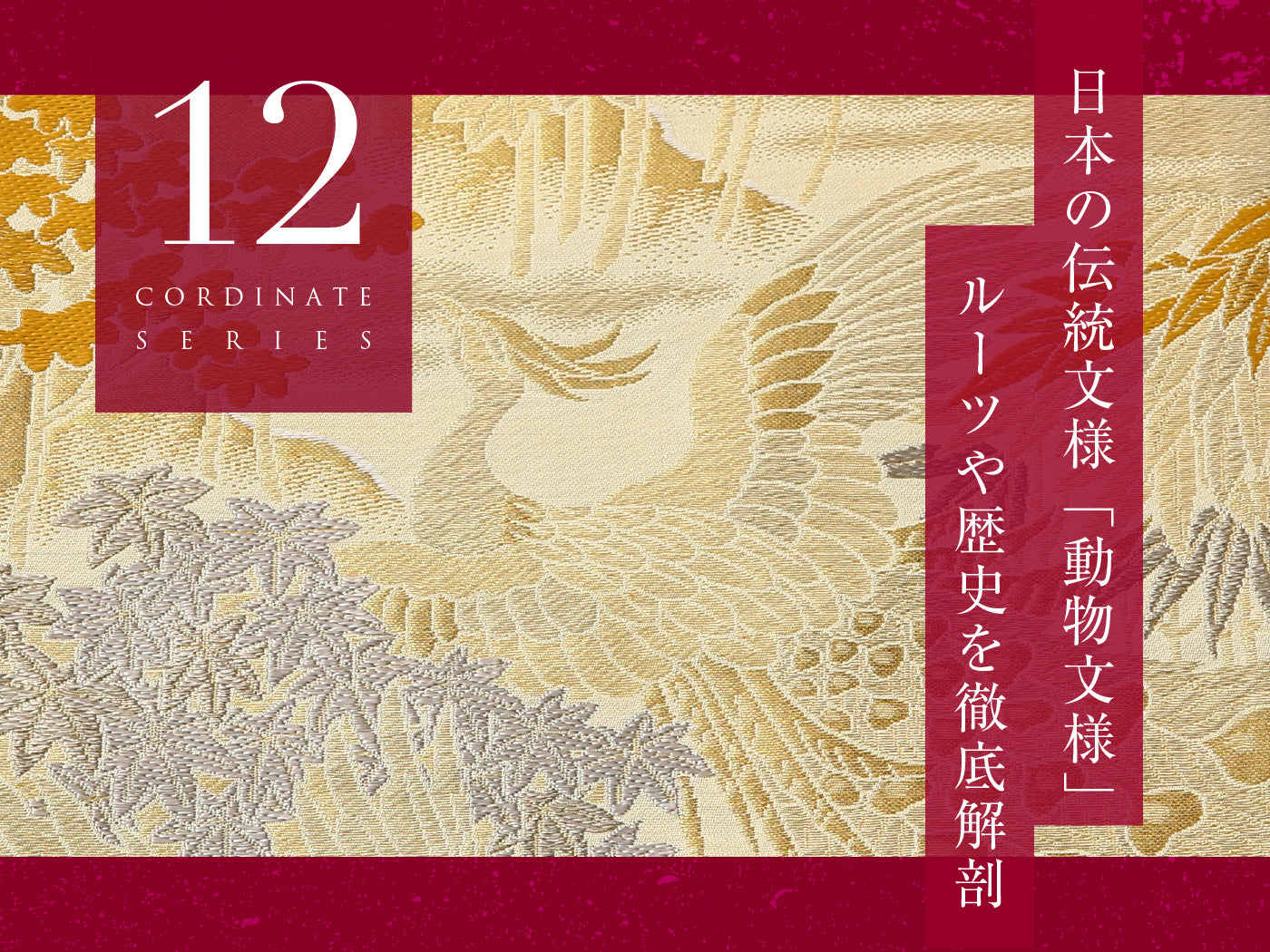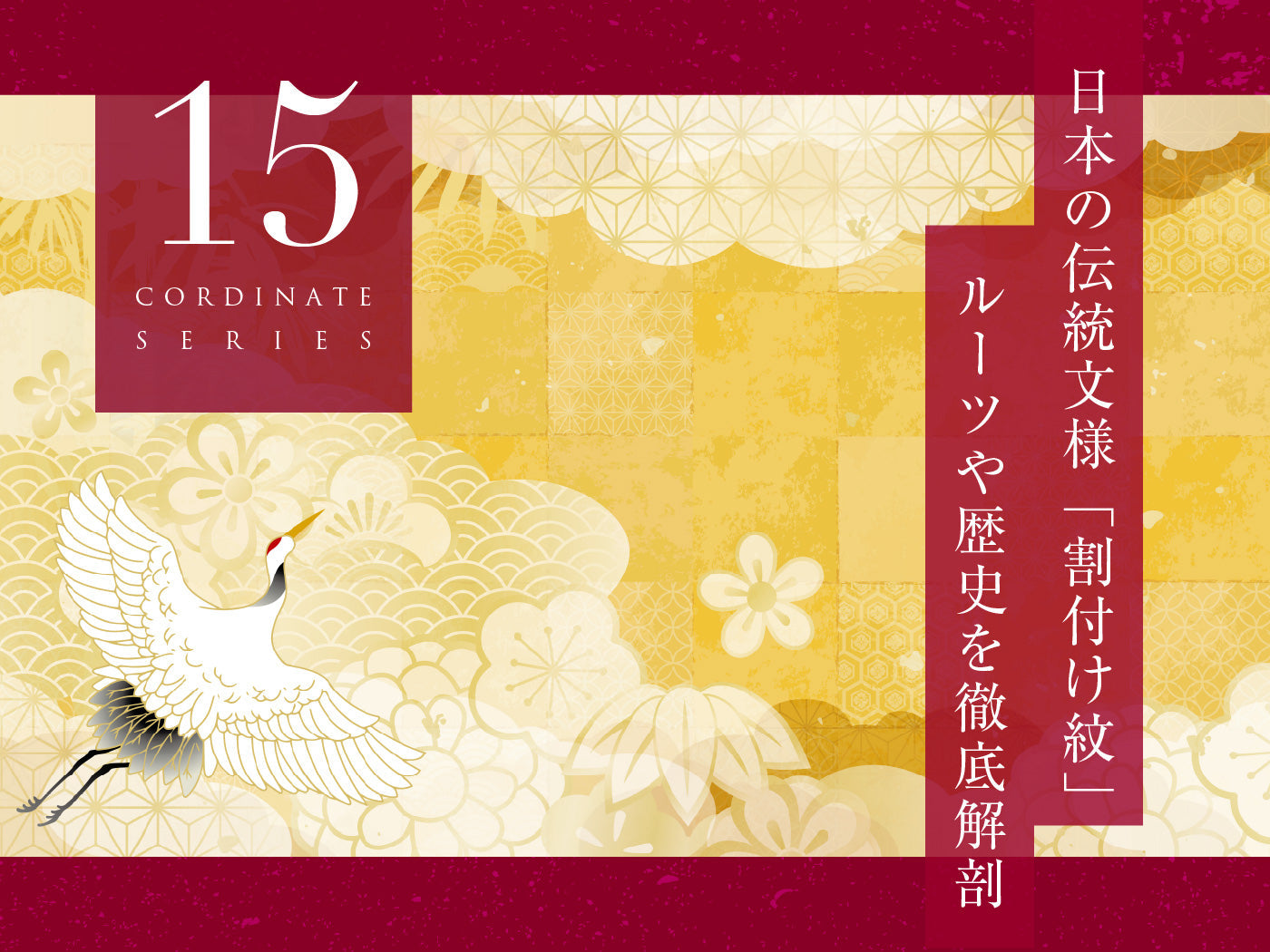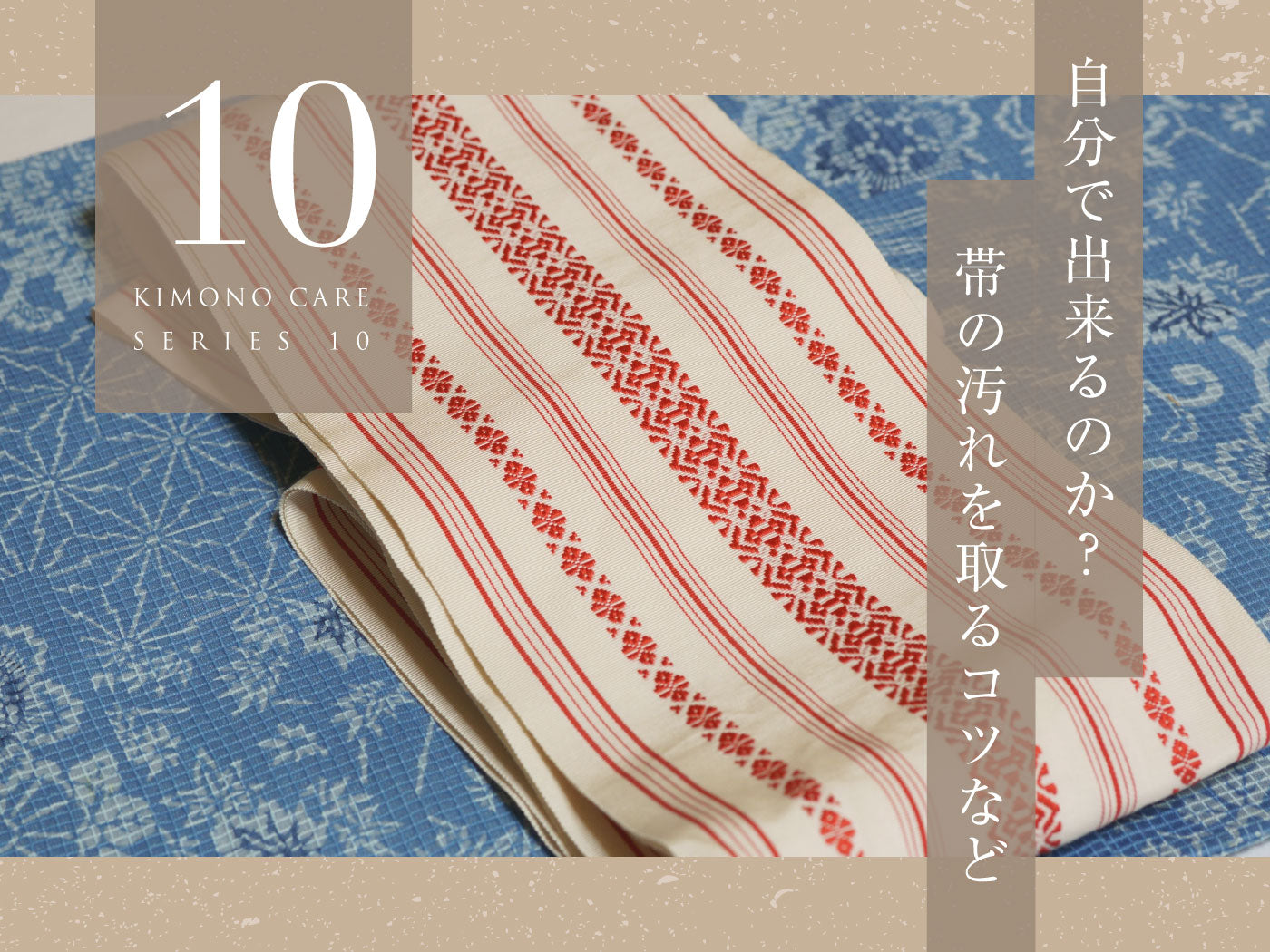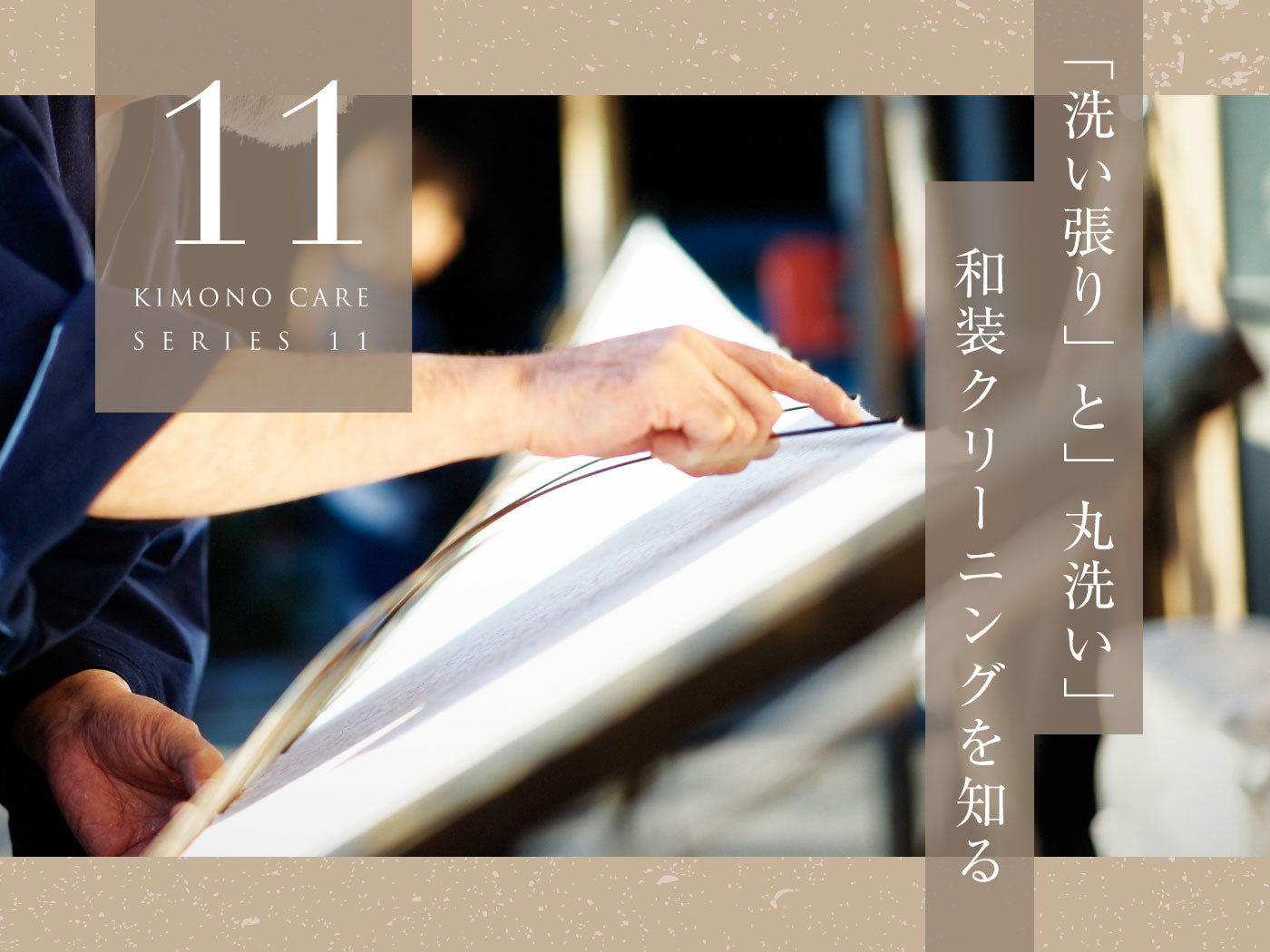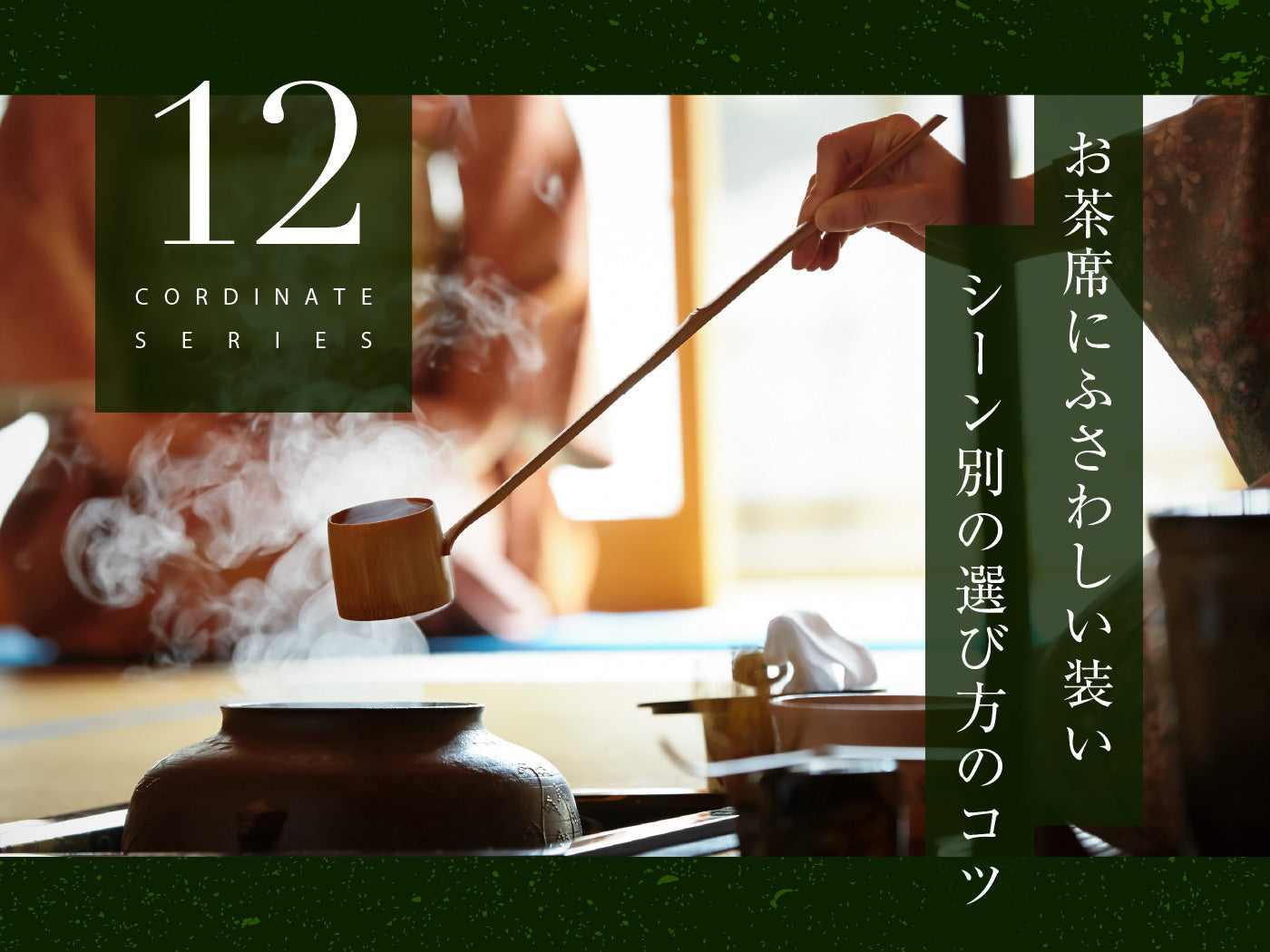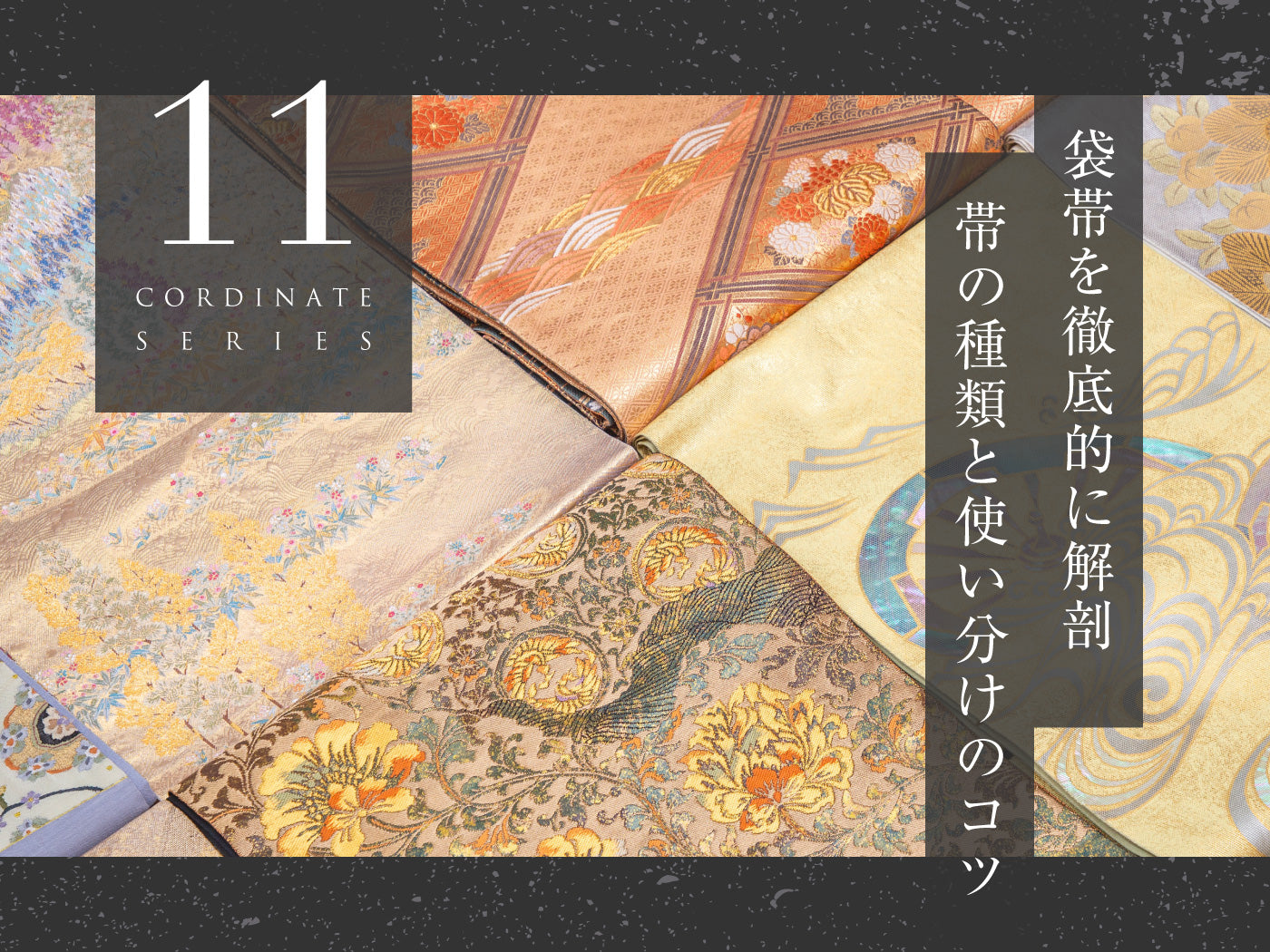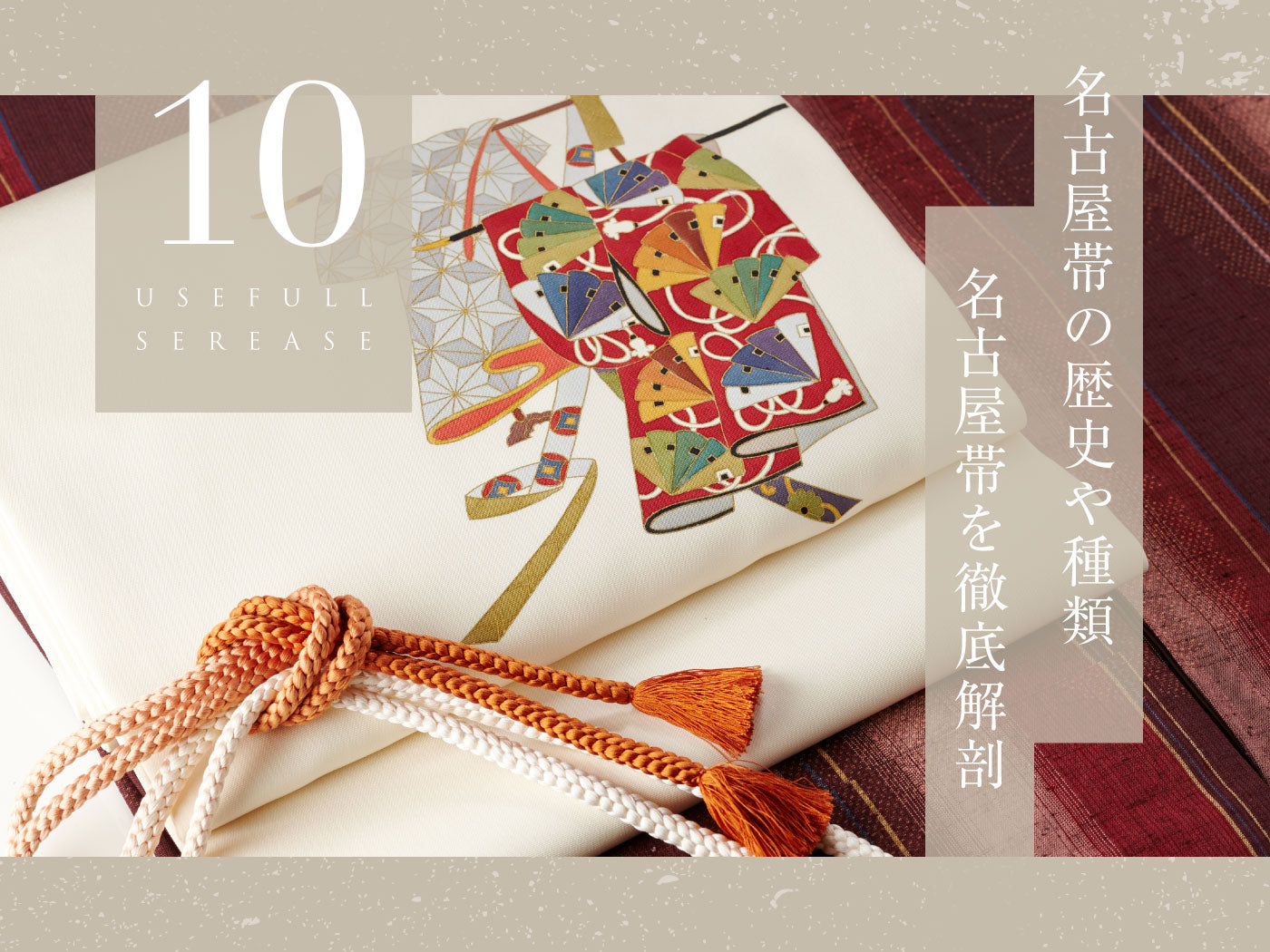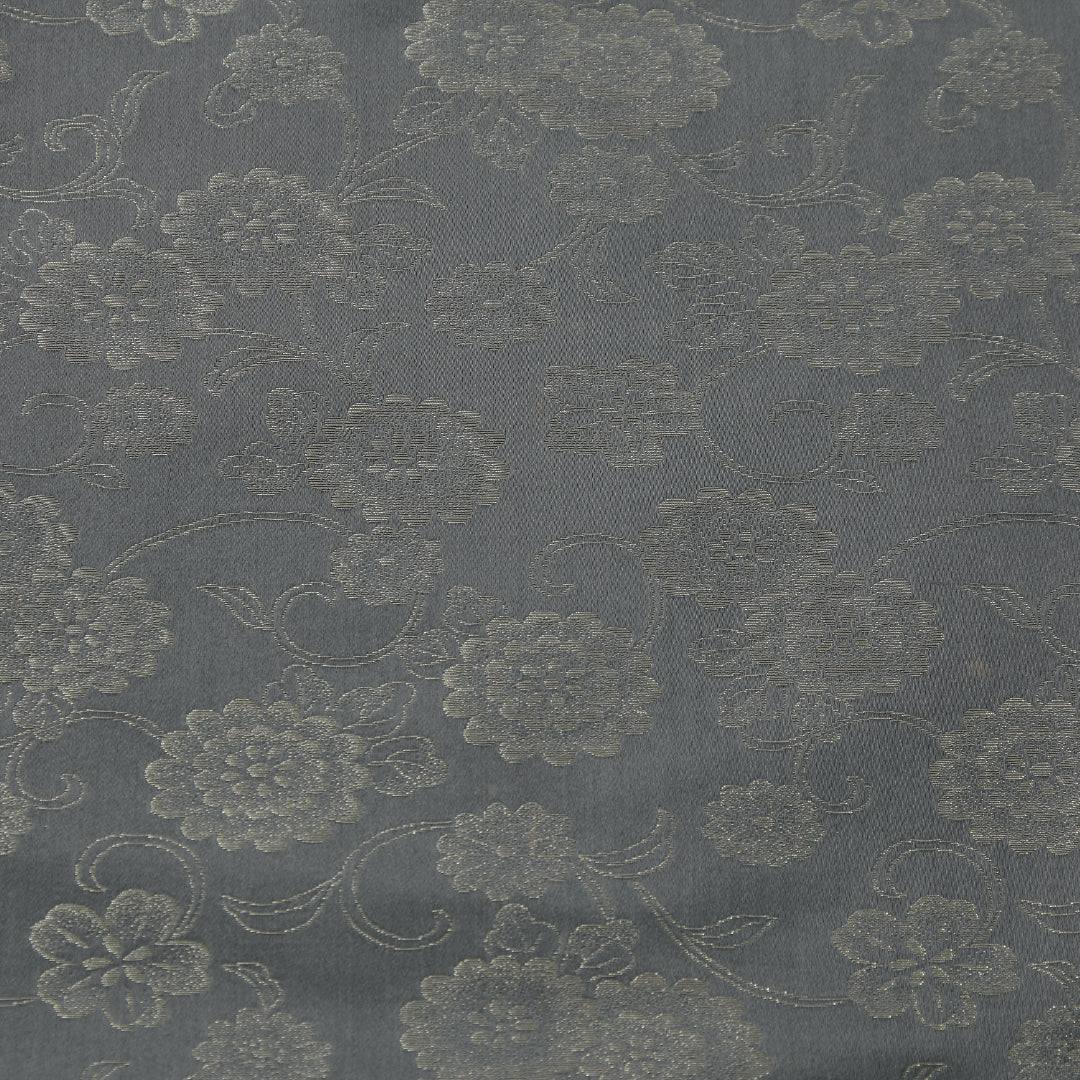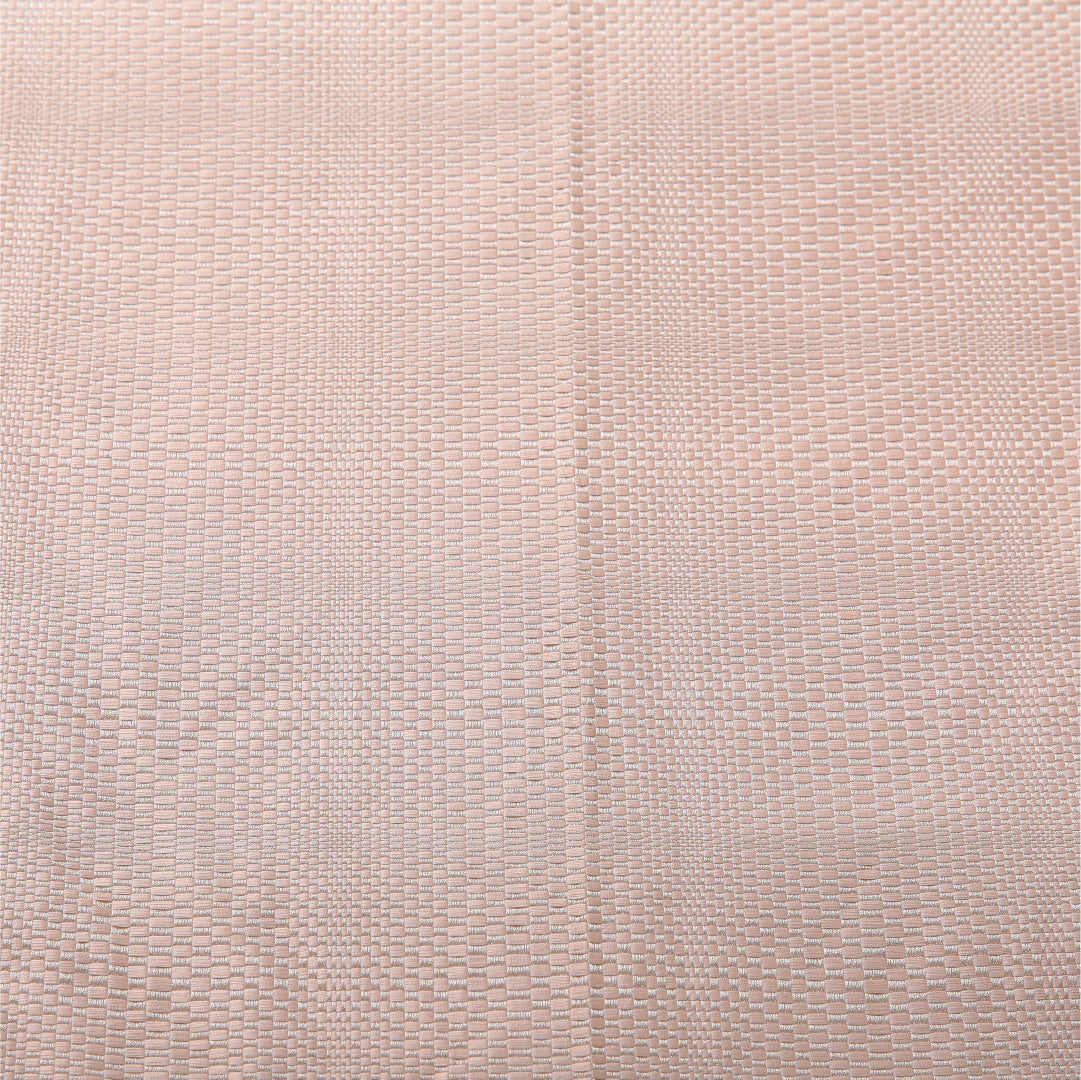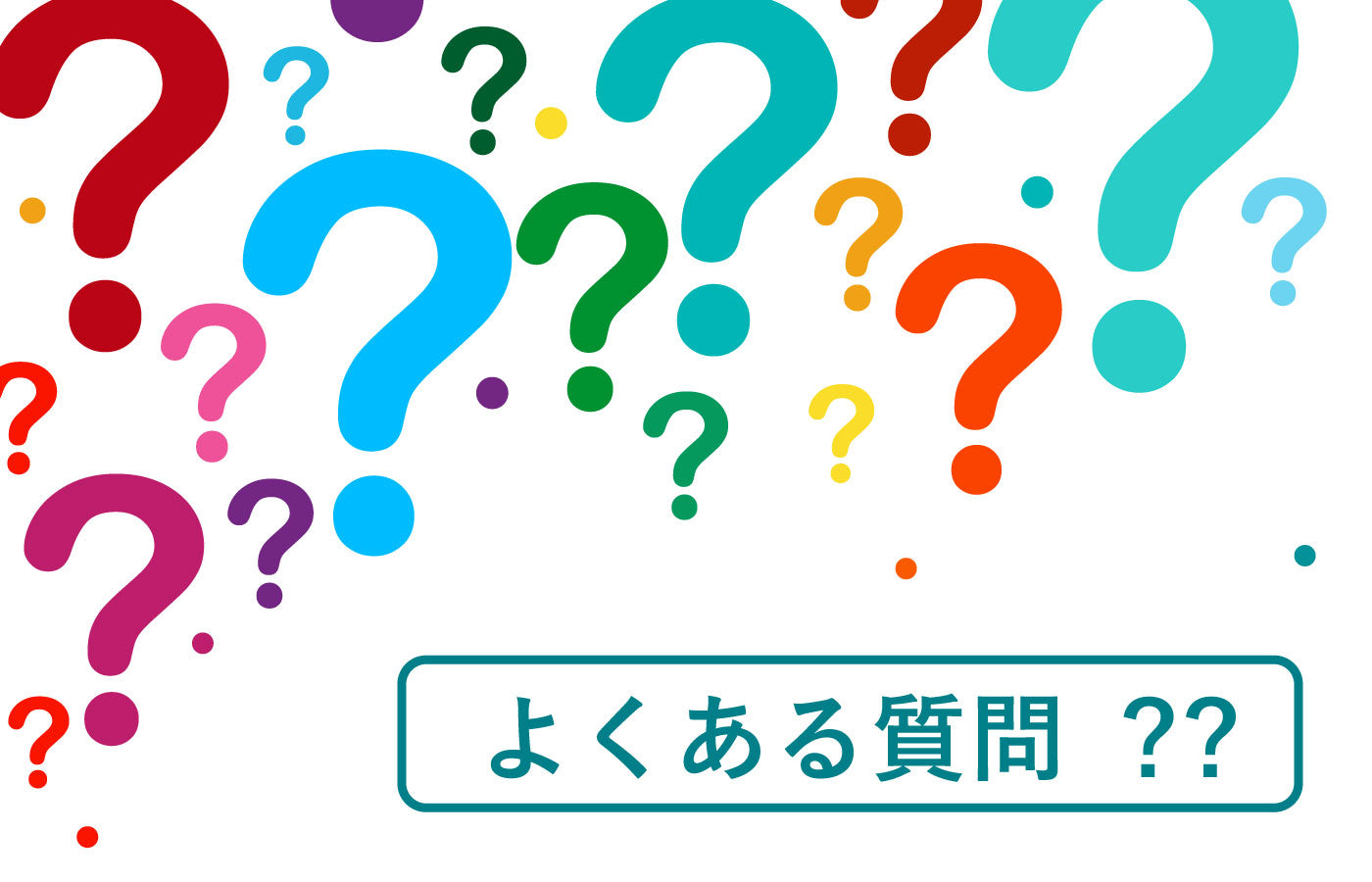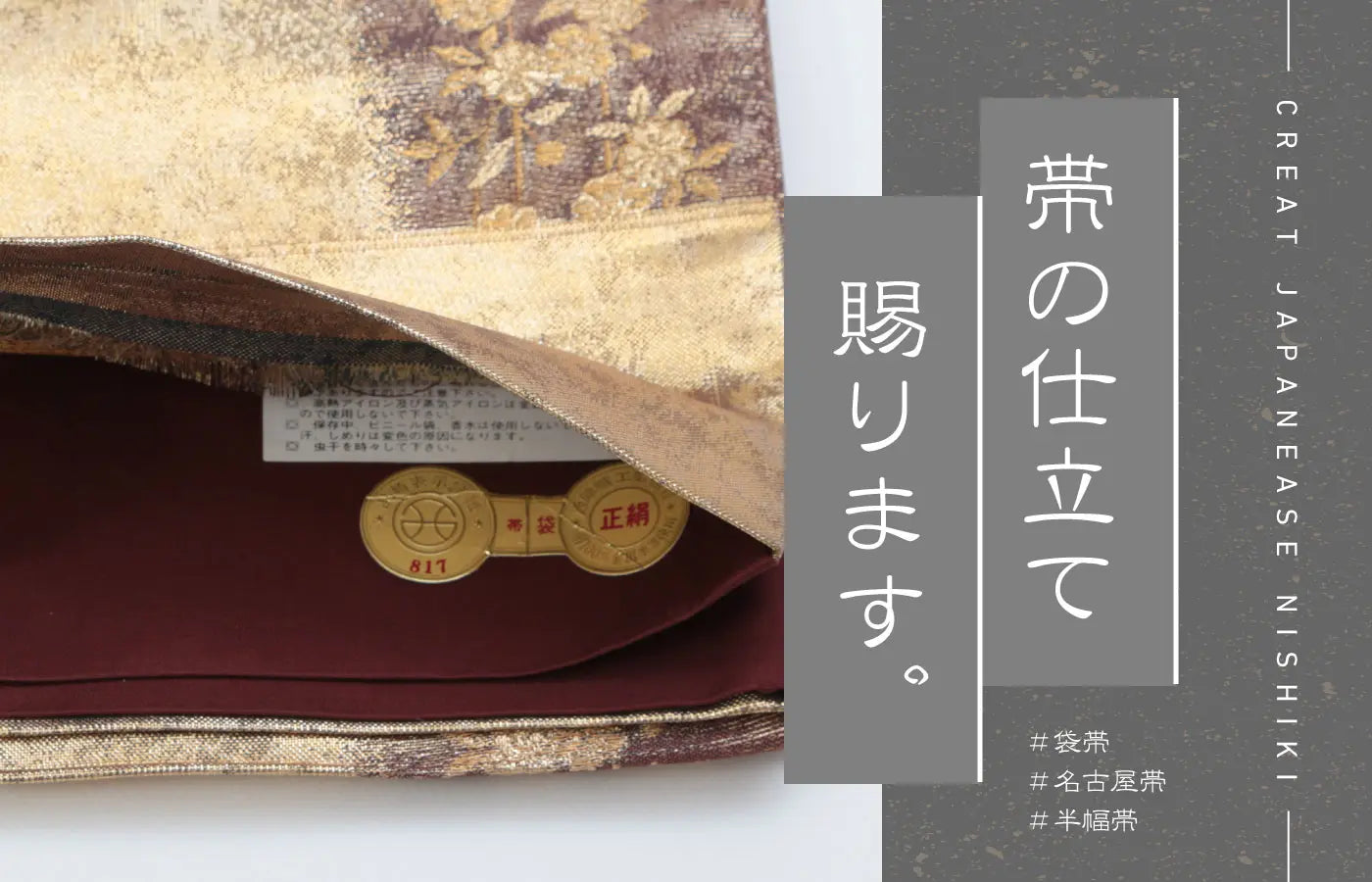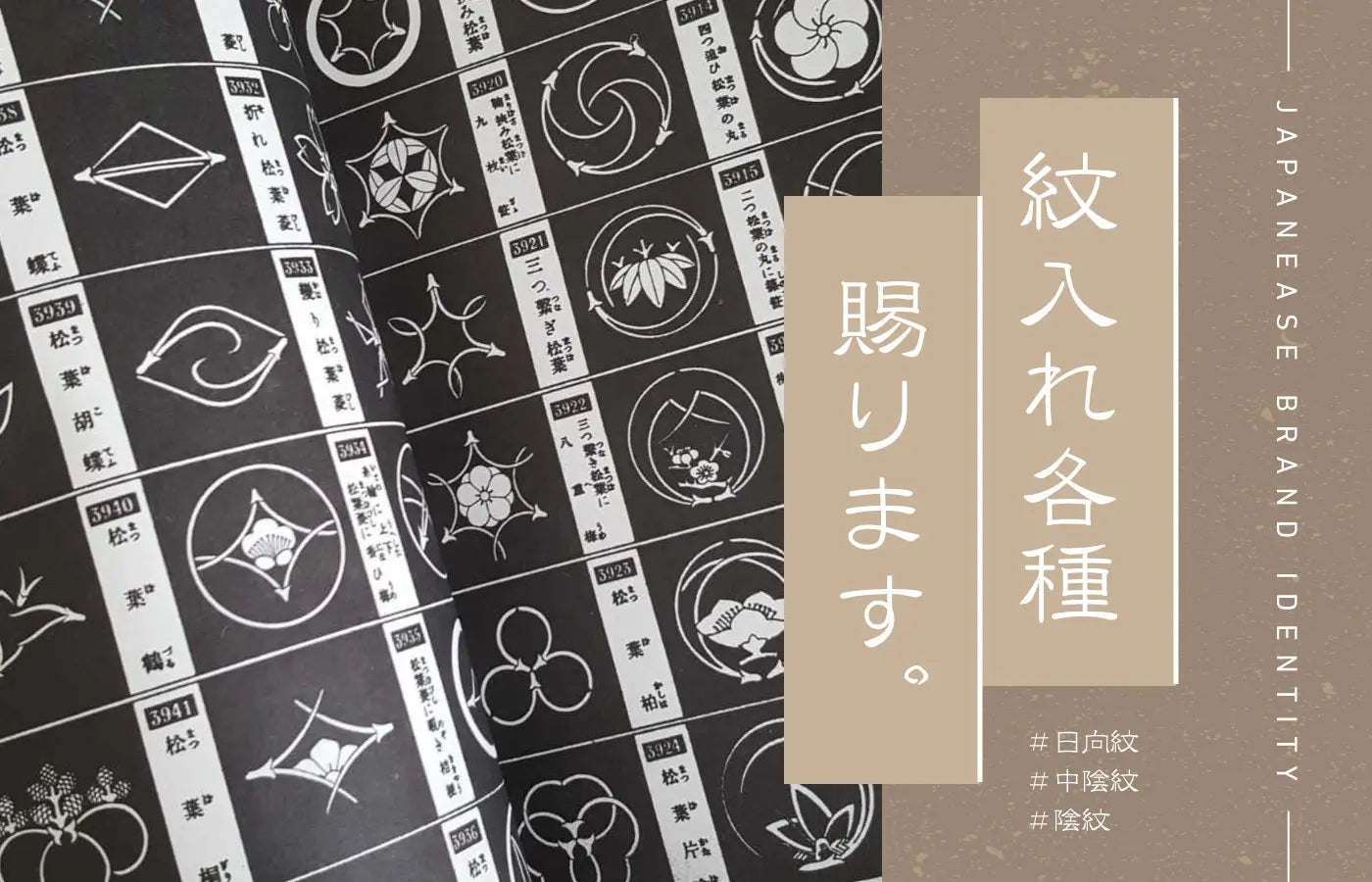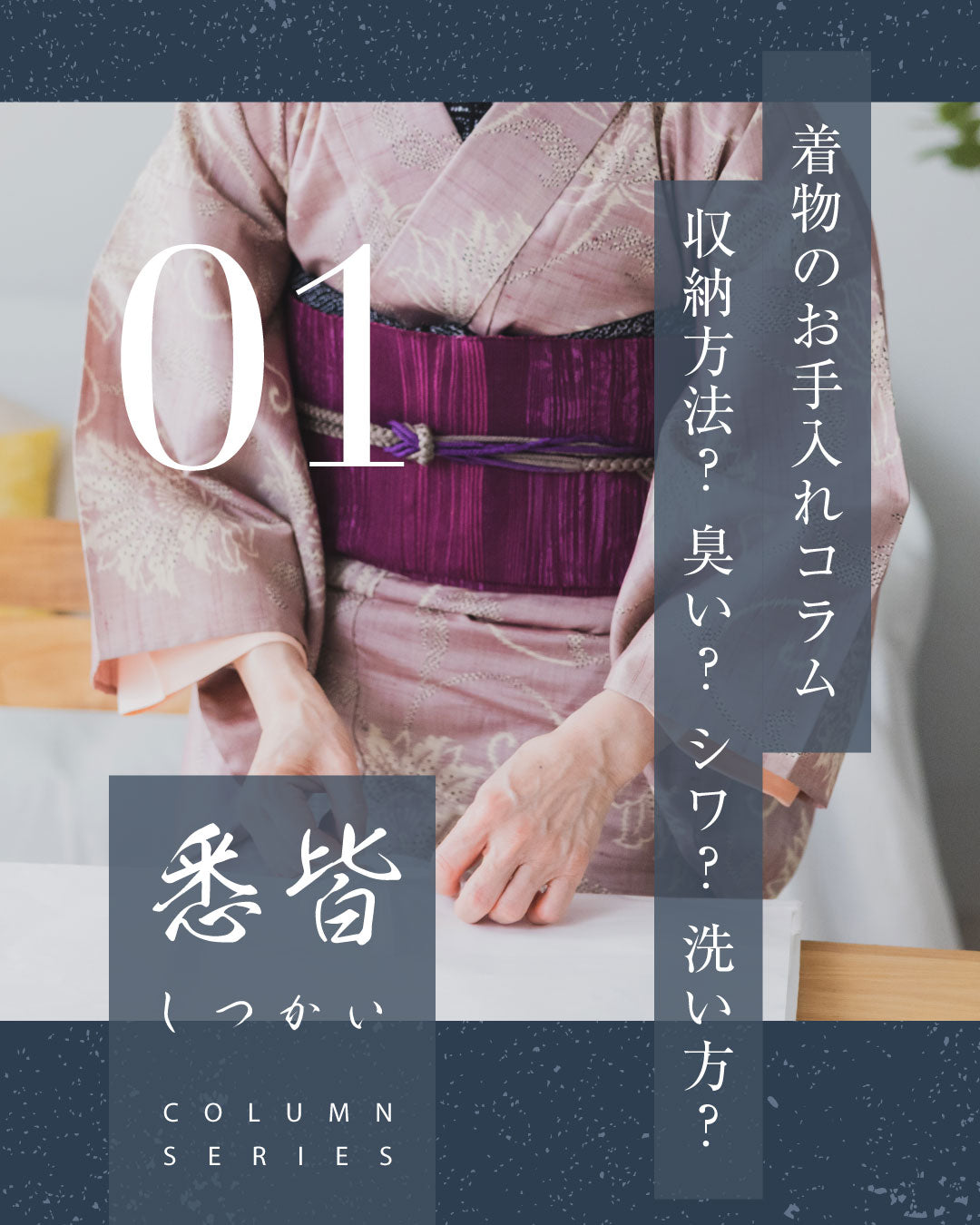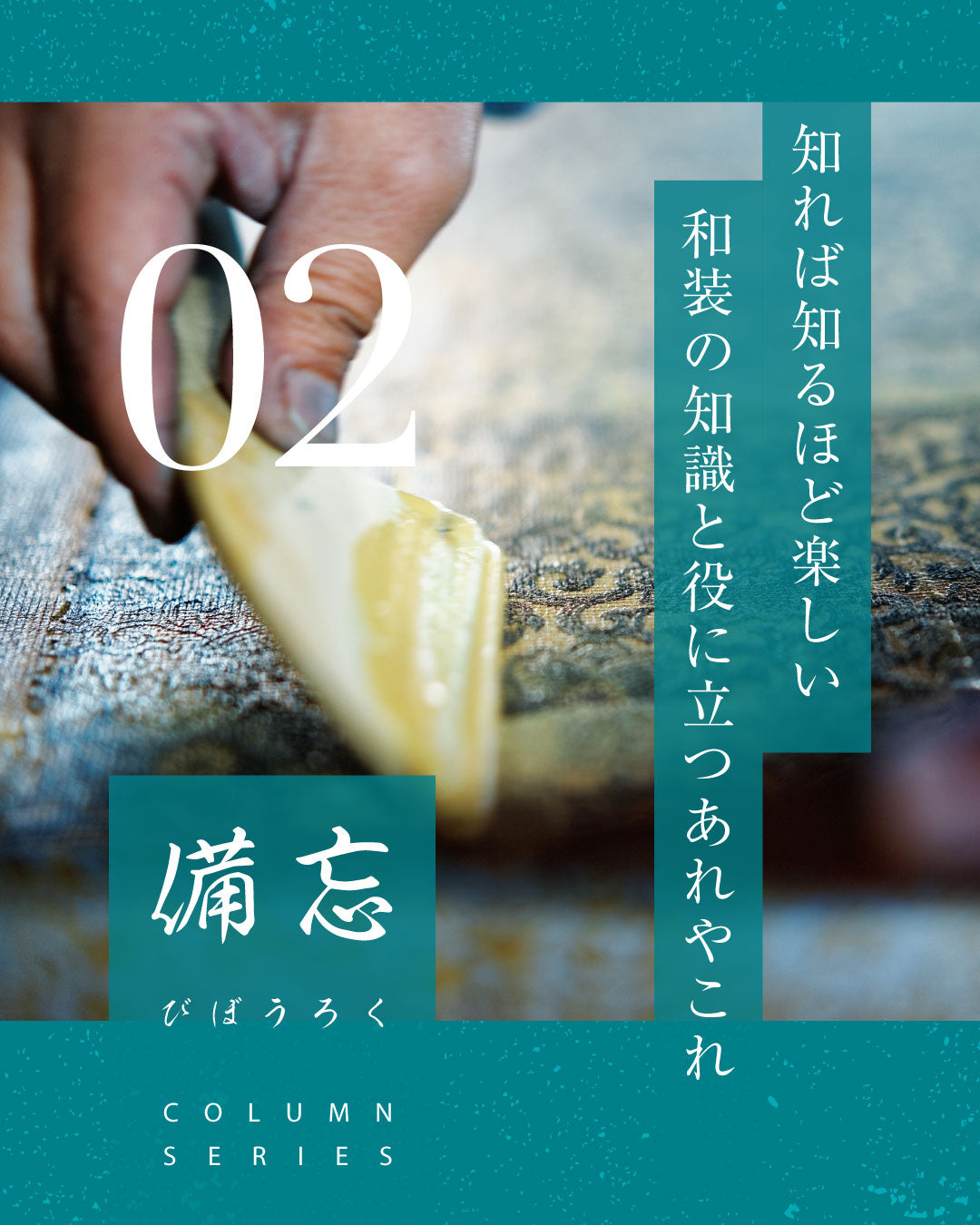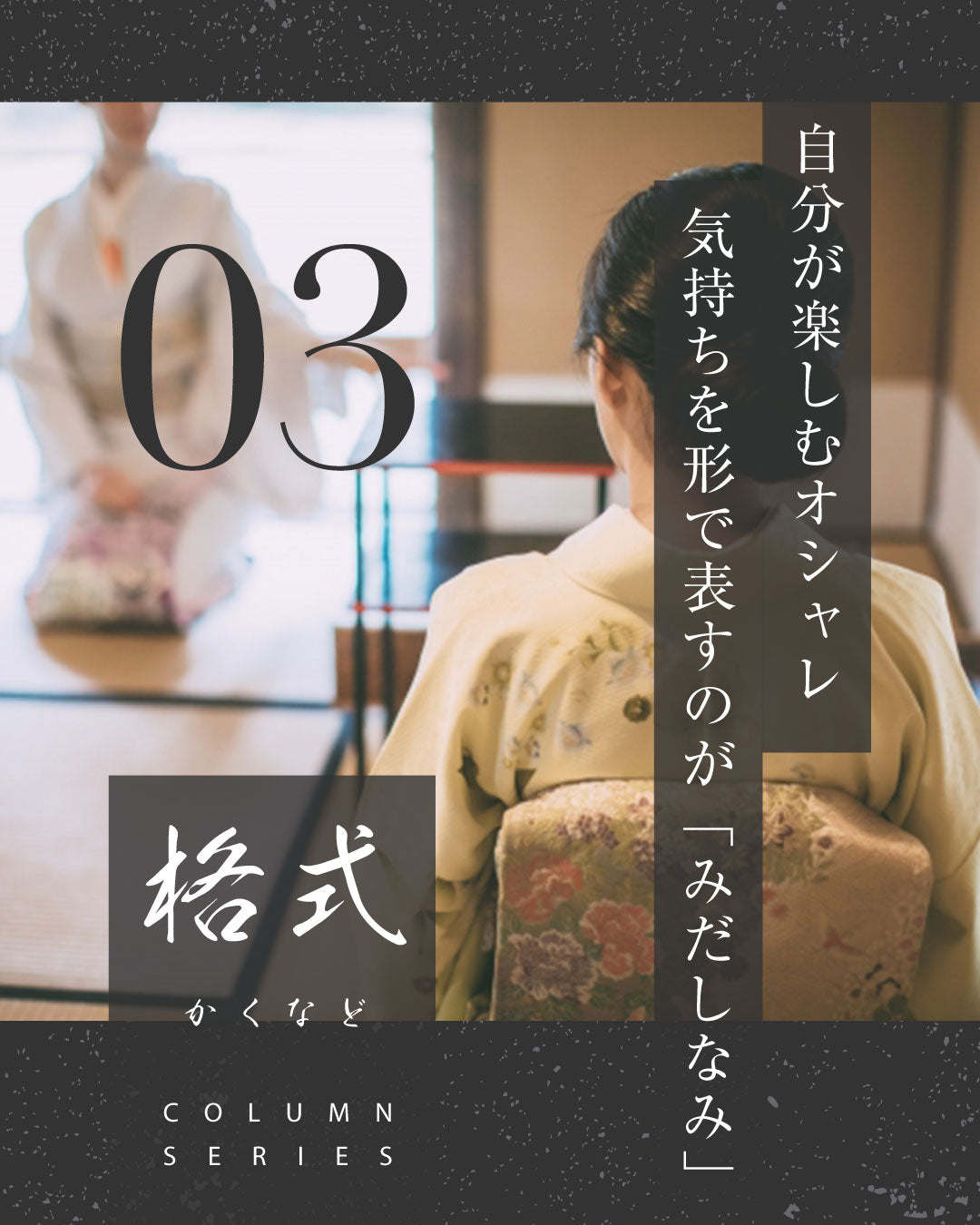帯揚げの格や着こなし、結び方とは? 小物で着物のコーディネートをもっと楽しもう
着物のコーディネートにおいて、印象を大きく変えるのが「帯揚げ」や「帯締め」などの小物の使い方です。
なかでも帯揚げは「結び方」や「見せ方」によって、全体の着姿が思っている以上に変わります。
若い人は多めに、大人は少なめに出すのが基本、とも言われますが、普段着のおでかけであれば、自由に着こなしましょう。
帯揚げは「素材」や「色使い」が個性を発揮するアイテムのひとつです。
今回は「帯揚げの基本」と「帯揚げの結び方」、そして「帯揚げコーディネートのコツ」をお伝えします。
帯揚とは?帯揚げが登場したのは江戸時代末期

「帯揚げ(おびあげ)」とは、帯の上側を飾るコーディネートアイテムのことで、帯枕(おびまくら)を包み、帯の形を整えるための和装小物です。
今では和装の定番アイテムとなった「帯揚げ」ですが、実は広く普及したのは、そんなに古くありません。
江戸時代末期、深川の芸者が太鼓橋の完成を祝って考案した「お太鼓結び」のために登場したものだといわれています。
さらに、一般の人が帯揚げを日常的に使うようになったのは、明治時代に入ってからだそうで、当時の抒情画には、女学生らしき若い女性たちが、帯揚げをたっぷりと覗かせている姿が描かれています。
華やかな銘仙に馴染む、にぎやかな色柄のものが多い印象です。

現代では無地感覚の淡い色合いのものが多く見られますが、普段のおしゃれとして楽しむ着物なら帯揚げに決まりはありません。
色柄だけでなく素材や結び方にもこだわって、個性的な着姿を極めるのも帯揚げの楽しみのひとつです。
帯揚げの種類と着用シーン

「帯揚げ」には様々な種類があります。代表的な素材の「正絹(しょうけん)」以外にも、木綿や麻、ポリエステルなど様々な素材で作られます。
最近ではレースなど、洋装用の生地をアレンジして、コーディネートを楽しむ方も増えています。
小紋や紬を代表とする「街着や普段着」として着物を楽しむ分には決まりはないので、ある程度の長さのある布であれば、帯揚げとして使う事ができます。
ちなみに、一般的な帯揚げのサイズは「160cm × 30cm」程度です。
ファッション要素のひとつとして、是非、自分好みの布で試してみてくださいね。
それでは、基本的な帯揚げの種類と、TPOの考え方について紹介して行きます。
総絞りはフォーマルに・部分絞りはカジュアルに

絞りの帯揚げには「総絞り」と「部分絞り」があります。総絞りの帯揚げはフォーマルな場でつかわれるのが一般的です。
はっきりした色の帯揚げは振袖に、白地に金糸を使った帯揚げは留袖に、淡いお色目の帯揚げは訪問着や色無地に使われます。
総絞りの帯揚げ一覧
また、部分的に絞りがある「部分絞り」や「飛び絞り」の帯揚げはオシャレ着用となります。
飛び絞りのなかでも、特に疋田絞りで花の中心部を白く残した「輪出し」と呼ばれる絞りを施した帯揚げは、年代を問わず人気の高い品です。
部分絞りの帯揚げ一覧綸子の帯揚げは色で着用シーン(TPO)が決まる

艶やかな光沢と滑らかな手触りの綸子(りんず)は、帯揚げの素材としても非常に多く利用されています。
ぼかし染めで2色以上に染め分けられたものは、コーディネートによって見せる色を変えられ、柄の入ったものは小物との組み合わせが楽しめます。
染めや織り模様も楽しい綸子ですが、するするとしているので、初心者さんには少し結びづらいと言う難点も。
難しいと感じたら、まずは縮緬の帯揚げで練習するのがおすすめです。
白地の綸子の帯揚げは黒留袖に

白地に金銀糸などが使われている帯揚げは、一般的に留袖に合わせます。
吉祥文様の入った袋帯に白の帯揚げは、留袖のスタンダードなフォーマルコーディネートとなっています。
淡い色目の綸子の帯揚げは色留袖・訪問着・色無地に

フォーマルシーンやセミフォーマルシーンでの訪問着や色無地、江戸小紋には淡い色目の帯揚げがおすすめです。
色に関しては帯や着物の色に合わせたコーディネートで問題はないでしょう。
鮮やかな色や濃い目の色は振袖や普段着に

鮮やかな色、はっきりとした色目の帯揚げは「振袖」や「街着・普段着」に向いています。
小紋や紬といったオシャレ着では、特に気にせずコーディネートを楽しんでください。

自分自身が主役の成人式などで振袖を着る場合は、着物のコーディネートに合わせた色目を選ぶのが良いのですが、結婚式や披露宴でゲストとして参加する場合は、淡い色目の帯揚げがおすすめです。
縮緬(ちりめん)の帯揚げはオールマイティに使える

ふっくらした質感とシボが特徴の縮緬の帯揚げは、結びやすく手に馴染むのも嬉しいポイントです。
素朴で味わい深く、柄がなくとも、しっかりとした存在感を持っています。
カジュアルシーンからフォーマルシーンまで幅広く使えますが、綸子のものと比べると、多少子供っぽい印象にはなるかもしれません。
絶対に失敗したくないという席では、縮緬の帯揚げは避けたほうが無難です。
色柄の種類も豊富で、値段もお手頃なものが多いので、好みのものを何枚かそろえておくのも良いですね。
夏物の帯揚げは通気性の高いものを

着物と同じように、帯揚げなどの小物にも季節があります。
帯揚げには絽や紗のものがあり、主に盛夏の時期に活躍します。
改まった場や結婚式などでは着物にあわせて薄物の帯揚げを選びますが、ちょっとしたお出かけ程度であれば、それほどこだわらなくとも良いでしょう。
とはいえ、夏のおでかけに縮緬はちょっと重いイメージです。
帯揚げは、着る人よりも見る人の印象を重視して選びます。やはり暑い時期には、色や素材で涼しさを演出しましょう。
帯揚げは帯枕が隠れれば小物としての役割を果たしますので、それほどしっかりしたものでなくとも困ることはありません。
レースや幅の広いリボンなどを使っても可愛いですね。
帯揚げの結び方
着物と帯の間にほんの少し見えるだけの帯揚げですが、結び方にはいくつかの種類があります。
振袖や浴衣のときには変わり結びで華やかに、粋にまとめたいときには入り組 (いりく) できりっと、と1本の帯揚げでもいろいろに楽しめるのが嬉しいところ。
ここでは基本的な帯揚げの結び方を3つ紹介します。
本結び

着付け教室などでならう、もっとも一般的な帯揚げの結び方です。
帯枕にかけた帯揚げをきれいにたたんで体の前でひと結びし、さらにもう一度結んで、中心は帯の中に入れ込みます。
結んだ先に余った帯揚げはたたんで帯の中にいれるとすっきりと、左右の帯揚げにはさむようにして入れ込むとふっくらと見えます。
帯揚げをどの程度出すかで、着こなしの印象は変わるもの。
年齢の他、細身の方は少なめに、ふくよかさんは多めに出すと、バランスが良くなります。
自分にあった出し方を探してみてくださいね。
入り組 (いりく)

帯揚げを結ばずに左右にからげ、そのまま帯の中に入れ込むと、中心に向かって斜めにまとまります。
それが「入」の字の形に見えることから、「入り組」と呼ばれる結び方です。
その形を羽に見立て、「かもめ結び」とも呼ばれるそうです。
本結びよりも大人っぽく、粋な雰囲気で、紬やお召にも良く似合います。
斜めの角度が大きくなると見える帯揚げの面積も広くなります。
また帯の上に出したり、衿もとにかけたりといったアレンジも。こちらは振袖で結ばれることも多い帯揚げの結び方です。
一文字

右前を長くとり、前帯の上にまっすぐ重ねます。帯の上には広く、まっすぐに帯揚げが見える結び方です。
結ばず、左右の端を帯の間に入れ込むだけなので、誰でも簡単にできるのもポイント。
総絞りの帯揚げで、成人式の振袖にもよく使われます。
左右のどちらかでリボン結びにしたり、飾り結びにして帯締めを重ねたりと、アレンジの幅も広い結び方です。
帯揚げのコーディネートのコツ
帯揚げや帯締めのコーディネートに迷ったら、着物や帯から1色を拾うのが良いとされています。
目立つ部分でなくとも、ほかのところにも使われている色なら、全体を見たときに調和がとれるからです。
しかし、帯揚げと帯締めの色が同じだと野暮ったいと感じることもあります。
特にアンティーク着物を今風に着こなしたいと思ったときには、定番の組み合わせは古臭く見えるかもしれません。
そんなときには、あえて着物や帯の色の捕色(ほしょく)を選ぶのもおすすめ。
捕色とは、色相・明度・彩度で色を分けた色相環という図の中で、反対側に位置する色同士のことです。
これは互いを補いあう色として扱われます。また、捕食に隣接した色は「反対色」と呼びます。

たとえば赤の捕色は青緑です。反対色は青や緑。
こうした色を組み合わせることで、コントラストを強調したり、目を引くコーディネートにしたりすることができます。
いつもの組み合わせをちょっと変えたいと思ったときに、試してみてください。
まとめ

帯と着物の組み合わせがしっくりこない、というときは帯揚げの出番です。
帯揚げの素材や色で足し算・引き算をすることで、着物のコーディネートの幅がぐんと広がります。
リサイクル着物を違った雰囲気で着たい! と思ったときにも、帯揚げを変えてみてくださいね。
箪笥で眠っている帯や着物も、帯揚げ次第で、まだまだ活躍するかもしれませんよ。
帯揚げの商品一覧